
『DEATH STRANDING』は、一言で表すと「歩く」ゲームだ。
『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』(デススト2)をクリアして、このシリーズが歩くことを主題にしたゲームであることを改めて確信した。
しかし、ストーリー上の目標は明確に「分断された人々を繋げる」ことだ。歩くのはその間に横たわる過程にすぎない。
1作目が描いた分断は、図らずも発売の直後にコロナ禍というわかりやすい形で現実世界に座礁することになる。我々はウイルスによって物理的に分断された。
2作目が発売される頃、コロナ禍はただの日常となった。分断は1作目のころよりもっと根深く、今も現実に座礁したままだ。
本作で明確に何かを繋げるシーンは、各拠点にカイラル通信を繋ぐ瞬間だ。拠点に入り、□ボタンを押して端末にアクセスし、×ボタンを押せば完了。繋げること自体に労力は不要だ。ミニゲームが挟まることもない。

一方、過程である移動は、□ボタンを長押しして×ボタンを押すだけでは終わらない。
目的地にどのように向かうかはプレイヤーにゆだねられている。山岳やBTのいる難所を突っ切っても、迂回してもいい。どんな装備やルートを選ぶかも自由だ。
「この道を通っていけ」とゲームがプレイヤーに命令することはない。
それどころか、ストーリーの目的である「繋げる」ために歩かなくたっていいのだ。フォトモードのため、美しい風景を探して歩いたっていい。
そしてコントローラーを握り、スティックを倒すことで主人公サムは歩きだす。歩いているとバランスを崩したり、滑ったり、川に流されたりすることもある。こけそうになればL2やR2トリガーを引き絞る。戦闘が始まれば使うボタンもさらに増える。
同じようなルートでも、同じ移動はひとつとしてない。

それは初めから決められたムービーのように通路を歩くのではなく、自由に歩くため、このゲームを遊ぶということだ。
だからこのゲームは繋ぐゲームではなく、歩くゲームなのだ。
歩くこと、すなわち遊ぶことへの祝福を描いた『デススト2』は、私にとって素晴らしいゲームとなった。シリーズ作品を遊んできて、これほどまでに「報われた」と思ったゲームはないかもしれない。
だからこそ、本作に感じた違和感と、祝福への心からの感謝を記したいと思う。
※『デススト2』の本質に迫るため、ここから本作のネタバレが入ります。
『デススト2』のキャッチコピーは、芯を食っていない
今作に対して、私は前作以上に「なぜ繋がるのか」への答えを求めていたと思う。
『デススト2』には印象的なふたつのキャッチコピーがある。ひとつは副題である「ON THE BEACH」、もうひとつは「我々は繋ぐべきだったのか?」という問いだ。
特に後者は、前作で行ったことを再度見つめ直す良い機会だと感じた。
だが結果として、私は本作を象徴する言葉として、このふたつはどちらも適していなかったと思う。

まず、「ON THE BEACH」だが、こちらは本作よりも前作にふさわしい副題だと思う。前作では「ビーチであなたを待っている」(I’ll Be Waiting For You On The Beach)という言葉が印象的に挿入される。まさに「オンザビーチ」である。
この副題はネヴィル・シュートが1957年に発表した小説「渚にて」(On the Beach)が元になっているのだろう。核戦争を生き延びた一握りの人類が、真の終末を前にどのような行動をとるかを描いた作品だ。
潜水艦や人類滅亡といった共通項もあるが、『デススト2』とより重なるのは、「渚にて」から影響を受けた小説『復活の日』(小松左京)と深作欣二による同名の映画かもしれない。
潜水艦が重要なアイテムになる点は「渚にて」と同じだが、アメリカ大陸を徒歩で横断して仲間の元へと還る主人公吉住は、シリーズのテーマに繋がるものがある。
迂遠な繋がりではあるが、これでようやく、なんとなく「ON THE BEACH」である部分が見えてきた。しかし、どうしても副題に持ってくるほど本作の象徴になるとは思えない。
「オンザビーチ」は、やはり前作の副題にふさわしく見える。
つづいて、「我々は繋ぐべきだったのか?」という問いだ。少なくとも私の目には、ゲーム内でそれを強く問われたようには映らなかった。相変わらず人間は繋がる必要があり、サムやその仲間たちもあまりそのことに疑問を持たずに世界を繋いでいく。
確かに「縄は人を縛る」ことと、「縄が増えれば棒も増える」という2点はこの疑問のために描かれた。
棒は暴力の、縄とは絆と同時に、人を縛るものの象徴だ。
しかし、繋がることでいつか棒が不要になるという希望を描く側面が大きかった。
仲間に不信感を抱きながら、手錠端末で世界を繋いだ前作の方が、よほど繋ぐことへの希望と疑念をプレイヤーに提示していたと思う。そして、それでも繋ぐことでしか未来を紡げないことを描いた。
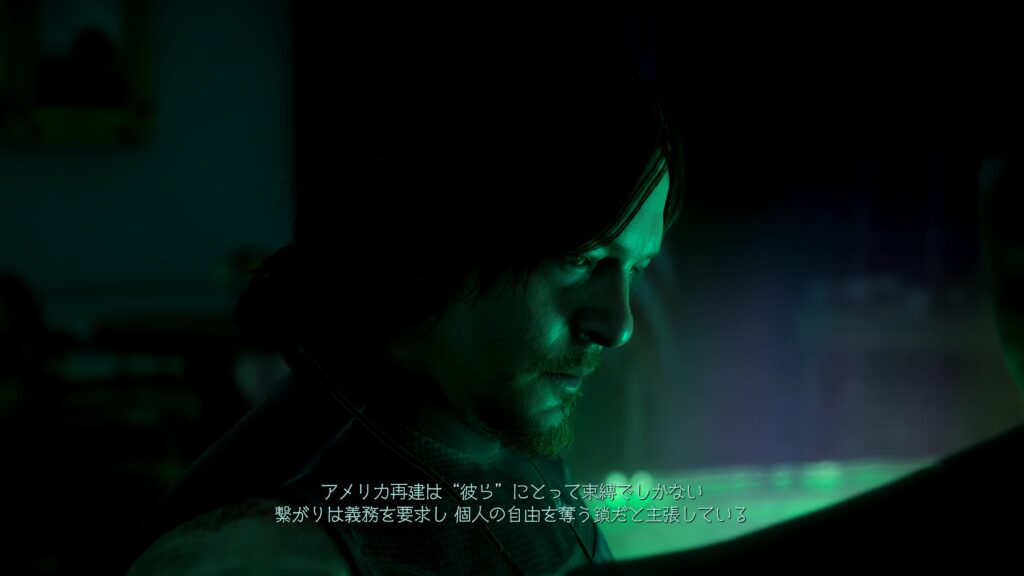
『デススト2』でも、やはり繋がるしか方法はなかった。そして、その繋がりによってサムはひとつの結末を得る。
その結末に「我々は繋ぐべきだったのか?」という疑問の入り込む余地はなかった。繋がなければ滅ぶのだ。
これはゲームが悪いのではなく、現実に問題があるのかもしれない。私には、繋がり尽くした先の未来がまだ想像できない。
この問いは、インターネットやSNSで繋がったことを示しているのだろうか。私には、それらはただの場であって、縄ではないように見える。SNS上で生まれる多くの繋がりは、快や不快によって一時的に同じ指向性を持っただけのもので、本作が描く命を賭けて結び目を作る縄とは異なるものだと思える。
「繋ぐべきだったのか?」
この問いを真に投げかけるべき時は今ではない。現実で人が繋がり尽くした後に必要になるはずだ。
「ON THE BEACH」は前作の方が似合っている。「繋ぐべきだったのか?」という問いは、今使うにはまだ早い。だからこそ、どちらも本質に届かなかったように思える。
やはり、このゲームは「歩く」ゲームだ
それを象徴するのが本作のメインテーマである「To The Wilder」だ。この曲が歌うのは、まさに歩くということだった。
この曲の歌詞は、まるでプレイヤーに語りかけるように、歩くことを讃える。
Bridge
To all the mountains, all the rivers
山を越え 河を渡る
To all the strays, the trailblazers
未踏の地をゆく迷える者たち
To what it takes to walk forever
さあ 歩きつづけるんだ
To what it takes to be who we are
ぼくらがぼくらであるために
Who we are
そのために
To the wilder,
荒野へ
To the wilder,
荒野へ
To the wilder you,
魂の荒野へ
『デススト2』では、なぜプレイヤーが歩くのか、ひとつの結論を提示している。
事件の黒幕の目的は「人類の移動の停止」であることが明かされる。身近な部分では「人類とBTが出会わないようにする」ためであり、ゆくゆくは全てを管理し停止させ「地球の支配権を人類から次の進化種へ移動させなくする」ためだ。
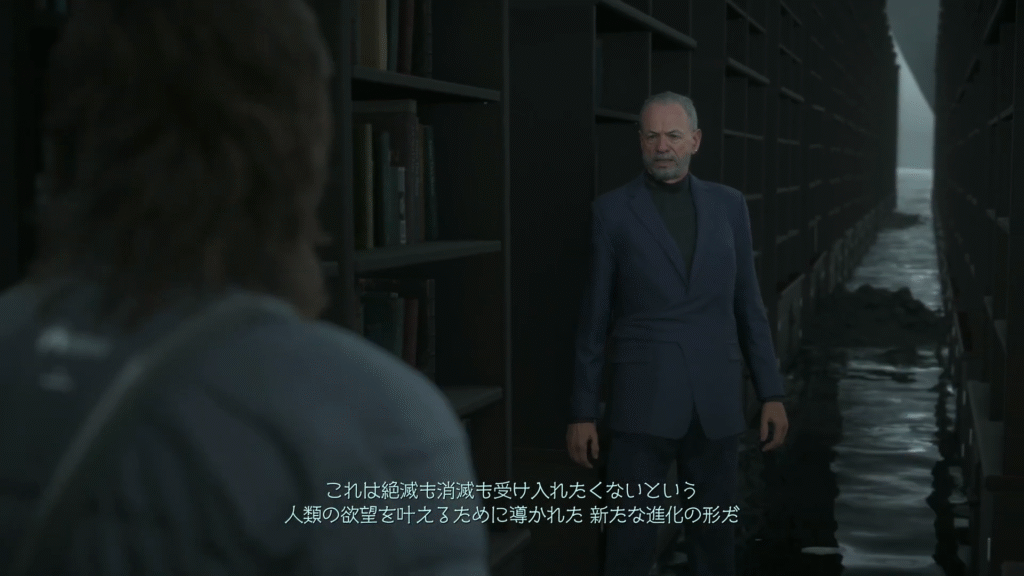
それを察知し、阻止しようと動いていたのが、「ダイハードマン」だった。彼は「自由に歩いて愛する者のところへ行く」「危険を承知で未知の世界へと足を踏み出す」と黒幕の主張をはねのける。移動こそ進化であり、未来なのだ。
そして「歩く」ことはまさに、プレイヤーがこれまで2作に渡ってつづけてきたことに他ならない。いつかは次の進化種への移動が起きるかもしれないが、危険を承知で荒野をなお歩く。
繋げるために歩き続けてきたこの旅路は、その実、歩き続けるために繋げる旅路だったのだ。目的は、やはり歩くこと、遊ぶことにあった。
ここでついに、ゲームのストーリーとプレイの目的がひとつに”繋がった”。
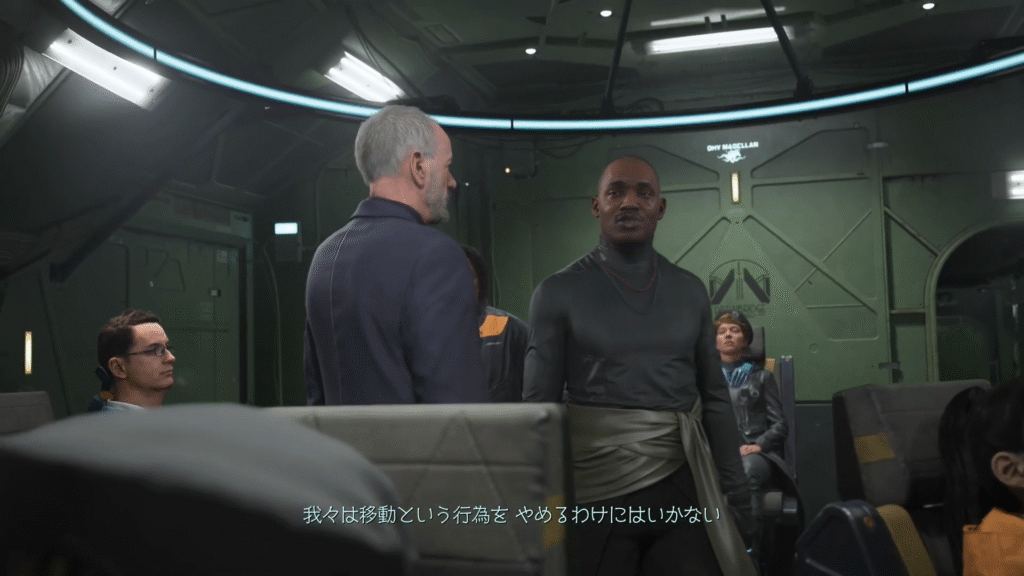
私はこれほどの「遊んでくれてありがとう」というメッセージを受け取ったことはないと思う。本当に、遊んで良かった。
歩くことへの祝福こそ、プレイヤーへの最大の賛辞。だからこそ、本作の副題はきっと「TO THE WILDER」であるべきだったのだと思う。
それがこの旅を終えてたどり着いた私なりの答えだ。
ゲームはエンディングを迎えたが、世界が終わったわけでも、全てが解決したわけでもない。サムの旅は終わらない。
端末に連絡が入る。お騒がせな”冒険家”がまたもや行方不明になったらしい。
さぁサム、荷物を背負って、また一緒に出かけよう。
(『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』と、作った全ての人への感謝に寄せて)

Special Thx:井戸の中の人々


コメント